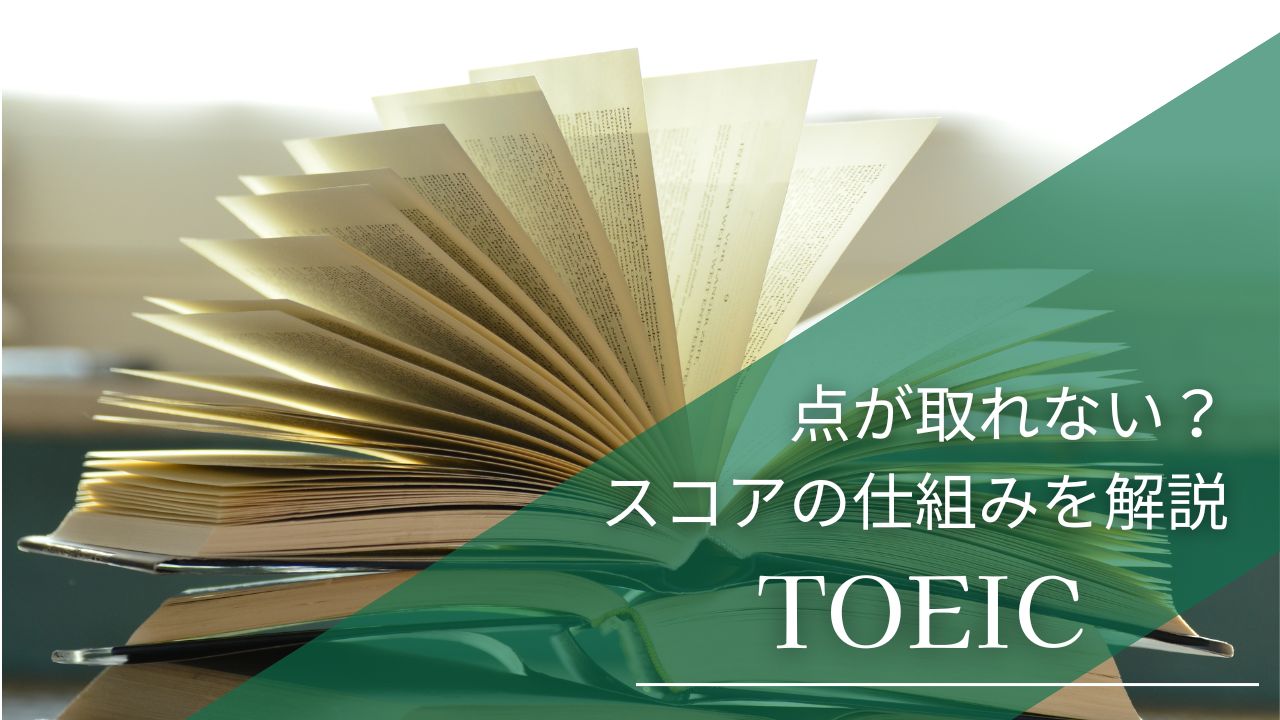最近、TOEICを受験して「以前より難しくなった?」と感じたことはありませんか?
リスニングの会話の複雑化や、リーディングの圧倒的な文書量。単なる形式の変化もありつつ、スコアそのものが伸び悩む傾向もあるようです。
実は、TOEICが難しくなったと感じる背景には、単なる「問題の難化」だけではなく、試験の採点構造と、受験者層のレベルアップが深く関係しています。
今回は、なぜスコアが取りにくくなっているのか、その裏側を考察します。
1.TOEICのスコアは「偏差値」のようなもの
TOEICのスコアは、単純な正解数で決まりません。つまり「1問何点」という一律の採点ではないのです。
毎回、受験者全体の正解率やスコアの分布に基づいて統計的な調整が行われる「スコア等化」という仕組みが採用されています。これは、試験の回によって難易度にばらつきがあっても、スコアの公平性を保つためです。
たとえば、もしある回の試験が簡単で、多くの人が高得点を取ったとします。この場合、スコアは厳しめに算出されます。
逆に、難しい回では、スコアは甘めに算出され、平均点が極端に低くならないように調整されます。
この仕組みは、例えるなら「偏差値」のようなもの。
他の受験者と比べてどのくらいの位置にいるか、相対的に示されているのが「TOEICのスコア」です。
2.TOEICエキスパートが難易度を押し上げる
TOEICには、毎回受験して満点を目指す「TOEIC攻略のエキスパート」が存在します。
英語上級者であることは言うまでもありませんし、中には講師業の方が研究や自己研磨のために受験されています。彼らは、試験の傾向や出題パターンを熟知しており、毎回のように980~990点を取得します。ちなみに、TOEICの満点は990点です。
エキスパートは少数派かもしれませんが、高得点層が固定化されると全体の平均点を確実に押し上げます。そして、平均点が上がれば上がるほど、統計的に算出されるスコアはより厳しくなります。
つまり、以前なら900点取れた正解数でも、平均点が上がったことで900点を下回ってしまう、といった現象が起こりやすくなるのです。
容易に満点を取れてしまうようでは、試験として差別化も難しくなります。
結果として、より複雑な文脈理解、難解な語彙、多様なシチュエーションを問う問題が増え、試験全体の難易度が上がっていると考えられます。
3.難しくなったからこそ、本質的な英語力が問われる
形式の変更や、エキスパートたちの存在によって、TOEICが難しくなったと感じるのは事実かもしれません。しかし、それは決して悪いことではありません。
以前のTOEICは、特定の対策をすれば高得点が取りやすい面もありました。英語の意味がわからなくても、テクニックやパターンで解ける問題があったのです。
しかし、現在のTOEICは、より多様な情報を素早く処理する能力や、文脈を正確に読み解く「実務直結の英語力」がなければ太刀打ちできません。
実際、Part 7のマルチパッセージに出てくる、メールや資料を照らし合わせる問題は、海外営業部門や外資系企業で、日常的に行われる業務そのものです。
つまり、TOEICは単なる「試験」ではなく、ビジネスや日常生活で使える「本物の英語力」を測るためのツールへと進化していると言えます。
4.受験対策:必ず最新の公式問題集を解く
TOEICの出題傾向は、単語や文法知識だけでなく、文脈を正確に理解する力を問うものが増え、より実践的な英語力が求められるように変化しています。
そのため、本番の出題意図を正確に把握するためには、古い教材ではなく、最新の公式問題集が不可欠です。
今のTOEICは「なぜこの答えになるのか」という論理的な推論を重視しています。
公式問題集を解く際には、単に問題を解くだけでなく、答え合わせの後に1問1問「なぜこの答えになるのか」を深く考え、出題者の意図を読み解くトレーニングをすることで、この難化傾向に対応できる力が身につきます。
参考までにですが、私は公式問題集のPart 7の問題と答えを全て精読(自力で和訳)した後、初めて900点を超えることができました。
最後に
「TOEIC満点は990点」という上限が決まっている以上、試験の権威を守るために問題が難しくなっていくのは、英語に限らず自然な流れと言えます。
受験で利用される英検も一昔前より格段に難化していますし、TOEICもまた、企業の採用や評価に直結する試験として、より高い「業務処理能力」を求めるようになっています。
例えるなら、「男子陸上100m走で、9秒台を出さないと決勝に残れない時代」になったようなものです。
個人的に最近のTOEICで感じるのは、以下の2点です。
- 構造理解:
基礎文法と語彙を重視し、問題全体の意味や構造を理解しているかをしっかり問われる問題が増えた - 処理スピード:
問題を読み返していると全問解き終わらないため、情報を一読で理解して判断するスピードがこれまで以上に求められている
TOEIC特有の引っ掛けもありますが、テクニック的なことはさておき、まず何よりも基礎固めが最優先。それから、理解した文章を何度も繰り返し学習し、英語を英語のまま処理するスピードを上げていくこと。
自分の英語力を本物へ引き上げるチャンスだと捉えて、最新の傾向と共に一歩ずつ進んでいきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。